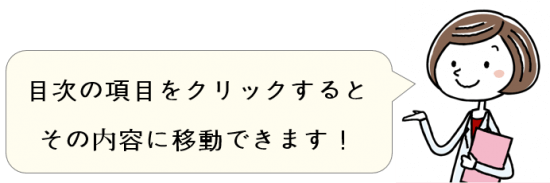美容外科・形成外科ビスポーククリニック上野佐知先生へのインタビュー記事です。
今回は、美容医療に取り組む先生の考え方や姿勢、お得意とされている傷跡を残さない婦人科形成の施術の工夫など、細部にわたりお聞かせいただきました。
婦人科形成を検討されている皆さまにはとても参考になります。

医師上野佐知 先生
経歴
2006年3月大阪医科大学医学部医学科 卒業
2006年4月大阪医科大学附属病院 初期臨床研修医
2008年4月大阪医科大学付属病院 形成外科
2009年4月橘会東住吉森本病院 形成外科
2010年4月東邦大学医療センター 大橋病院 形成外科
2016年4月東京臨海病院 形成外科
2017年4月銀座よしえクリニック
2021年10月美容外科・形成外科ビスポーククリニック東京院 入職
・臨床研修指導医
・日本形成外科学会認定形成外科専門医
<所属>
・日本形成外科学会
・日本美容外科学会(JSAPS)
・日本美容外科学会(JSAS)
・日本頭蓋顔面外科学会
・日本創傷外科学会
1.はじめに
「美容外科・形成外科ビスポーククリニック上野佐知先生へのインタビュー」をお届けします。
今回のインタビューでは、先生の美容医療に取り組む姿勢や考え方、ビスポーククリニックの特徴や傷跡を残さない婦人科形成の施術などのこだわりを細部にわたりお聞かせいただきました。
インタビューを通して、とても真摯な姿勢で美容医療に取り組まれていること、また最近では、婦人科形成の施術への抵抗が小さくなっていることを知りました。
さらに、ビスポーククリニックの特徴についても理解することができました。
美容医療や婦人科形成をご検討されている方には、とても参考になると思いますので、ぜひ、チェックしてみてください。
2.美容外科・形成外科ビスポーククリニック 上野佐知先生インタビュー
Q1.形成外科医を目指されたきっかけは何でしょうか?また、美容医療を志すようになったのはいつからでしょうか?
大学医学部1回生だった時に、各診療科の紹介を受けるという授業がありました。
その際、形成外科の紹介で、術前・術後の写真を見る機会がありました。
その写真を見た際に、術前の状態が手術によって大きく改善されていることに衝撃を受けました。
形成外科における手術の力が、患者さまにとって、とても大切であると感じました。
これが形成外科を目指そうと考えたきっかけです。
その後、研修医としても形成外科を選びましたが、最初に感じた印象とまったく変わらず、形成外科医としてキャリアを積む決心をしました。
その後、大学病院を退職した際、美容皮膚科からお声をかけていただき、そこに就職しましたが、しばらく、そこに勤めていて感じたのは、美容皮膚科では外科手術に関わる機会が限られることです。
そこで、自分自身が培ってきたキャリアをフルに生かせる可能性を追求し、美容外科にチャレンジすることにしました。
やはり、私は外科系の仕事が好きなんだと感じています。
Q2.上野先生の美容医療に取り組む際のモットーやミッションについてお聞かせいただけますでしょうか?
美容医療は、保険診療と異なり特定の病気を治すというゴールがあるわけではありません。
美容が持つ本質的な特性上、患者さま一人ひとりの好みによってゴールが変わってきます。
だから、カウンセリングの際は個々の患者さまとしっかり話し合いながら、好みや目指しているゴールを探ることを強く意識しています。
そのため、施術の前には患者さまとのコミュニケーションを密に取るようにしています。
手術そのものは、医師の手に委ねられるので、始まってしまえば患者さまに話す術がありません。
だからこそ、術前のゴールのすり合わせはとても大切だと感じています。
Q3.患者さまとのゴールのすり合わせは、具体的にどんな方法で行われているのでしょうか?
鼻の手術などは、3Dのシミュレーションソフトを使って術前に患者さまの考える術後のイメージのすり合わせを行うことができます。
過去に施術をした症例写真を見ていただいたり、患者さま自身がインスタグラムのモデルさんの写真などをもって来られたものを一緒に見ながら話し合っています。
最近では、モデルケースになる写真が比較的簡単に得ることができるので、その点で医師と患者さまとのすり合わせの精度向上に役立っていると感じています。
Q4.婦人科形成がお得意と聞いていますが、具体的に内容を教えていただけますでしょうか。また、特にこだわっておられることについても教えていただけますしょうか?
婦人科形成とは女性器全般の治療です。
ビスポーククリニックで多いのは、小陰唇の縮小や産後の膣のゆるみを縮小する手術です。
当院では、傷跡をできるだけ目立たなくしたい、つまり最終的に美しい仕上がりにしたいというこだわりがあります。
またビスポーククリニックでは婦人科形成の施術の場合、基本的には真皮縫合と表面の縫合を行い、抜糸を行うような治療方針としています。
傷跡の美しさを追求するためには複数の層で縫合し、緻密に形成するのが良いと考えているからです。
真皮縫合より表面縫合の方が密に縫合できるため、真皮縫合した後にさらに一針一針細かな調整が可能で、傷をぴったり合わせることが可能になります。
ただし患者様のご希望によっては、できるだけ細かく真皮縫合した後に、表面を縫合せず皮膚用ボンドで合わせることも可能です。
そうすることで抜糸不要になるため、患者様の術後の負担を減らすことができます。
| メリット | デメリット | |
| 縫合・抜糸のある施術 | 施術後の仕上がりが美しい | 縫合・抜糸のない施術と比べるとやや侵襲が大きい |
| 縫合・抜糸のない施術 | 施術の侵襲が少ない | 縫合・抜糸のある施術と比べると仕上がりの美しさがやや劣る |
Q5.婦人科形成の術前・術後の感染予防のためにどんなことを行っておられますか?
特別なことではないと思いますが、感染予防のポイントには次のようなことが挙げられます。
- 生理周期のチェックを行い、施術生理の期間と重ならないように注意する
- 施術の翌日からシャワーなどが可能なので、創部を清潔に保っていただく
抗菌薬は術中投与に加え、術後にはルーティンで内服投与を行っている
こうした点をしっかり行えば、感染リスクはそれほど高くないと考えています。
Q6.術後の傷に緊張が加わるとコラーゲン産生が亢進するということですが、この点について対策を教えていただけますでしょうか。
どの部位であっても術後の傷に緊張が加わると、コラーゲン産生が亢進します。
コラーゲンが増えると傷は盛り上がるため、傷跡が目立つ原因になってしまいます。
そのため複数の層で縫合して緊張を分散したり、目立つ部位でなければ術後にテーピングをしたりして、傷跡に緊張が加わることを予防し、傷を目立たせないよう工夫しています。
婦人科形成の場合はテーピングを行うことが困難な場所なので、複数の層で縫合することや、場合によってはコラーゲンの過剰な産生を抑えるトラニラストという内服薬を併用することで対策をします。
Q7.婦人科形成術の工夫や、多い症例について具体的に教えていただけますでしょうか。
-どんな症例が多いのでしょうか?
デリケートゾーンのお悩みを抱えて受診される患者さまの中で多いのは、小陰唇縮小術です。
このお悩みは、婦人科形成の手術の中でメジャーなものになり、20代や30代前半の患者さんが多いです最近では、V.I.O脱毛が一般的になってきているので、それにともなって小陰唇の形を気にされる若い女性が増えてきたと感じています。
また、特に若い女性にとって、美容医療を受けるハードルが下がってきたことも患者さんの数が増えている要因だと思います。
-小陰唇縮小術の際に工夫されることは何でしょうか?
工夫していることというか、気を付けている事として、手術の際、小陰唇を大きく切りすぎないでバランス良く形成することが大切だと考えています。
一旦、切除してしまえば 元に戻らないので、その点はとても注意深く施術します。
-施術後の注意点はありますか?また、どのくらいで日常生活に戻れるでしょうか?
膣は粘膜組織に近いので、血行が豊富で比較的キレイに傷が治るパーツです。
一方、血行が豊富なため出血しやすいという特徴があります。
施術後の注意点としては、出血を抑えるために、術後すぐはできるだけ安静に過ごしていただくように患者さまにお話しています。
また、施術後1~2週間でほぼ元の生活に戻ることができます。
しかし、傷が治るまで3ヶ月〜6ヶ月かかります。
傷が治る過程では、コラーゲンが増えるなどで、触れると違和感があるといったことがあります。
-効果の持続期間は、どれくらいでしょうか?
小陰唇縮小の施術は、患者さまが満足されれば、追加で施術することがなく、半永久的に効果が持続します。
そのため、追加の治療は不要です。
Q8.ビスポーククリニックには多くの形成外科出身の医師がおられますが、美容外科に携わっておられる医師との違いは何でしょうか?
私自身の経験から感じていることとしては、形成外科出身の医師のほうが、施術などで何かのトラブルが起こった場合の対処の引き出しが多いのがメリットだと思っています。
美容医療に携わっている医師の多くは、施術のターゲットが顔中心になります。
一方、形成外科は全身がターゲットです。
また、そこで美容目的ではないさまざまな症例を経験します。
そのため、トラブルを経験した場合の対処法の引き出しが多くなると思います。
Q9.施術や知識の研鑽はどのようにされているでしょうか?(学会活動など)
まず、美容医療の学会には、定期的に参加して知識をアップデートするようにしています。
また、大学時代の形成外科の同期生でも美容外科に進んだ仲間もいるので、ときどき意見交換して新たな知見を得るように努めています。
さらに、美容医療の経験が豊富な室孝明院長の指導を受けています。
いつも院長の手術をライブで見ていますが、とても的確でかつスピーディです。
「自分が同じレベルでできるのか?」と自問自答しながら見ていますが、自分の技術を高める模範としてとても参考になります。
Q10.患者さまへのカウンセリングやコミュニケーションで意識していることはどんなことでしょうか?
患者さまは日々、鏡でご自身の顔を見ています。
だから、自分のことを最もよくご存知です。
一方、私は患者さまが気づかないことで、より美しくなるような提案をプロの視点でできれば良いなと考えています。
たとえば、患者さまご本人は、鏡で見た自分自身の目が気になっているとします。
一方、私が客観的に「引き」で見た場合、輪郭に手を加えたほうが、より印象が良くなると感じることがあります。
そんな場合は、患者さまに、そのことを提案するようにしています。
そして、両者の話合いを通して、患者さまが納得された場合は、提案した施術を行います。
もちろん、患者さまのご希望を最優先しますが、コミュニケーションが円滑にいかない場合は、術前の写真やシミュレーションソフトの写真を見せて話し合ったりすることで、納得いただけるように努めています。
Q11.仕事、プライベートを含め、最近嬉しかったことはあるでしょうか?
仕事については、手術が無事終了し、ダウンタイムも終わって満足された患者さまの姿を見た際は、いつも嬉しいです。
プライベートでは、10歳の長女と二人きりで外食する機会があって、ゆっくりと食事と会話を楽しめたことです。
会話をしながら娘の成長を感じとれたことは、とても嬉しかったです。
普段、仕事の関係で帰宅が夜遅くなります。
だから、自宅でも一緒に食事を取る機会が週の半分くらいしかありません。
しばらくこうした機会がなかったので、二人でゆっくりと過ごせる時間を持てたことは、とても良い機会になりました。
Q12.上野先生が、ご自身の日常生活で美容やスキンケアで気をつけている点があれば、教えていただけますでしょうか。
実は、私はシミができやすい肌質です。
そのため、ビタミンCやトラネキサム酸の内服で対策をしています。
また、月1回くらいのペースで定期的に光治療(フォトフェイシャル)を受けています。
フォトフェイシャルとは、IPL(Intense Pulsed Light)と呼ばれる広範囲の光を照射する治療法のことです。
シミやくすみ、赤ら顔(酒さ様皮膚炎)、毛穴の悩み、肌のキメが粗いなどさまざま肌トラブルを同時に解消することができます。
肌へのダメージが少なく、ダウンタイムもほとんどありません。
皮膚科医療では多くの専門医からも支持されている治療法ですが、私のお気に入りの1つです。
化粧品に関しても、良いと思うものは試しています。
あとは、美容のことをご存知の方には常識ですが、顔を擦らないことや紫外線対策はしっかり行っています。
私は肌が弱いほうではないので、日焼け止めに関してはノンケミカルタイプではなく、紫外線ブロック力や使用感を重視し、紫外線吸収剤入りでSPF50+やPA++++のものを使うケースが多いです。
また、使い方に関しては、こまめに塗り直すことも意識しています。
Q13.患者さまはクリニックを選ぶ上で、どんな点に気つければ良いでしょうか?
選んだ美容クリニックが、患者さまご自身に合っているかどうかは、実際に受診してみないとわかりません。
だから、まずカウンセリングを受けて、そこの医師の治療方針や考え方に納得できるか、人柄に共感できるかなどを確認されれば良いと思います。
また、鼻の美容整形など大きな施術を受ける場合は、複数のクリニックで相談してから、最終的にどこで施術を受けるかを決めるのも良い方法だと思います。
Q14.患者さまの過度な期待をコントロールするために何か工夫はあるでしょうか?
アンチエイジングの美容医療は、1回で治療が終わるわけではありません。
施術が終わった瞬間から患者さまのエイジングが進むので、小さな治療を長期で続けることが大切であるとお伝えするようにしています。
Q15.初めて受診される患者さまにお伝えすることはありますか。
ビスポーククリニックを受診される患者さまは、他院修正で来られることも多く、比較的、美容医療を受けることに、慣れている方が多いです。
だから、受診前にホームページで十分に情報を収集して、不明な点や疑問点をメモにして、カウンセリングの際にそれを見てお話されます。
初めて受診される方は、緊張されていると思いますので、特に大きな施術を検討している際のカウンセリング時は、今、お話した慣れた患者さまのように、聞きたいことをメモしておいてその場で見ながら医師とお話されることも良い方法だと思います。
Q16.美容医療に興味があってもまだ経験のない方へのメッセージがあればお願いします。
私が多くの女性たちを診てきて思うことは、早めから美容医療などでケアを積み重ねておられる方にキレイな方が多いという印象を持っています。
たとえば、顔のたるみの場合なら、目立ってから美容医療を受けるよりも目立つ前から予防美容的に細く長くケアを続けておくほうが良いと思います。
また、シミなどの肌悩みは従来に比べて安全面や価格面でも治療が受けやすくなっています。
こうしたことはなかなか美容医療を受けた経験がないとわからないので、信頼できるかかりつけの美容クリニックを持つことで、何でも相談できる環境をつくることも良い方法だと思います。
そうすることで、治療のハードルも下がりますし、肌老化が進む前にケアがしやすくなります。
今では、20代後半や30代前半でアンチエイジングの美容医療を受ける方もたくさんおられます。
私自身も、振り返ると30代半ばでお肌の曲がり角を感じたので、アラサーからアンチエイジングを意識した美容医療の受診を考えても良いのではないかと思っています。
また、最近ではホームケアの美容機器やエイジングケア化粧品なども進化しているので、それらを使って継続してエイジングケアを行うことも選択肢の1つになりますね。
今回のお話が、美容医療に興味があるけども、まだ経験のない方にとってお役に立てば幸いです。
3.編集後記
今回のインタビューでは、形成外科医のキャリアを持つ上野佐知先生から、婦人科形成に関するお話をお聞かせいただきました。
インタビューでは、婦人科形成の施術時の工夫や傷跡を目立たせない方法、感染予防の対策などのお話を詳しくお伺いすることができました。
また、患者さまとのコミュニケーション、美容医療における患者さまとのゴールのすり合わせの方法などについてもお話しいただきました。
婦人科形成についてのお話を聞く機会は、私にとっては初めてだったこともあり、とても貴重な体験になりました。
この記事「美容外科・形成外科ビスポーククリニック上野佐知先生へのインタビュー」が、ナールスエイジングケアアカデミーの読者の皆様にとって参考になれば幸いです。
著者・編集者・校正者情報
(執筆:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)
京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務の後、医学出版社、医学系広告代理店勤務の後、現職に至る。
医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。
一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト
著作(共著)
(編集・校正:エイジングケアアカデミー編集部 若森収子)
大学卒業後、アパレルの販促を経験した後、マーケティングデベロッパーに入社。
ナールスブランドのエイジングケア化粧品には、開発段階から携わり、最も古い愛用者の一人。
当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。
そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報をご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。
ぜひ、ご登録をお待ちしております。
▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから
nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、お客様にご参加いただいた座談会やスキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。下記から、どうぞ。ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」
SNS Share
\ この記事をシェアする /