みなさん、こんにちは。
ナールスゲン配合おすすめのエイジングケア化粧品ナールスの公式ブログに来ていただきまして、ありがとうございます。
春の訪れとともに、毎年多くの人を悩ませる花粉症シーズンがやってきました。
「朝からくしゃみが止まらない」「鼻水がダラダラ流れて仕事に集中できない」「目のかゆみでメイクが崩れる」——そんな症状に悩まされていませんか?
花粉症対策といえば、マスクやメガネ、空気清浄機などの外側からのケアを思い浮かべる人が多いですよね。でも実は、内側からのアプローチもとても重要なんです。
花粉症は免疫の過剰反応によって引き起こされるため、食事によって免疫バランスを整えることで症状を和らげることができます。特に、抗炎症作用のある栄養素や腸内環境を整える食材を意識的に摂ることで、花粉に負けない体づくりが可能になります。
今回は、花粉症を和らげる食べ物&栄養素7選をご紹介!
「食事でできる花粉症対策」を知って、つらい春を少しでも快適に乗り切りましょう。
この記事のポイント
- 花粉症の症状を和らげるためには、免疫バランスを整え、炎症を抑える栄養素を意識的に摂取することが重要です。特に、ビタミンD、オメガ3脂肪酸、ポリフェノール、亜鉛は、免疫の過剰反応を抑えたり、粘膜を強く保ったりする働きがあり、花粉症の症状軽減に役立つ可能性があります。これらの栄養素を効果的に摂るためには、油と一緒に摂取する、加熱を避ける、毎日こまめに摂取するなど、吸収率を高める工夫が必要です。
- 花粉症対策に役立つ栄養素を効率よく摂取するためには、適した食品を選ぶことが大切です。特に、鮭、納豆、緑茶、牡蠣、ブルーベリー、えごま油、玉ねぎは、ビタミンDやオメガ3脂肪酸、ポリフェノール、亜鉛などを豊富に含み、花粉症対策におすすめの食材です。これらの食品を日々の食事に取り入れることで、免疫バランスを整え、花粉症の症状を軽減するサポートが期待できます。
- 腸内環境を整えることは、花粉症対策において重要な役割を果たします。腸には免疫の約70%が集中しており、腸内環境が乱れると免疫バランスが崩れ、アレルギー反応が過剰になりやすくなります。そのため、乳酸菌を含む発酵食品や食物繊維を積極的に摂取し、善玉菌を増やすことで、腸内フローラを整え、花粉症の症状を和らげることが期待できます。また、最近注目されている酪酸菌は腸のバリア機能を強化し、アレルゲンの侵入を防ぐ働きがあるため、花粉症対策として取り入れるのもおすすめです。
- 食事で腸内環境を整えることが理想ですが、毎日発酵食品や食物繊維を十分に摂るのが難しい場合は、乳酸菌や酪酸菌を含むサプリメントを活用するのも一つの方法です。BIOPORTは、高濃度の乳酸菌や腸のバリア機能をサポートする酪酸菌を含んでおり、効率的に腸活ができるサプリメントです。花粉症の症状を和らげたい方、腸内環境を整えて免疫バランスを正常に保ちたい方におすすめです。
1.花粉症対策に役立つ栄養素

花粉症の症状を和らげるために、免疫バランスを整え、炎症を抑える栄養素を積極的に摂ることを試してみてはいかがでしょうか?そこでまずは、花粉症対策におすすめの栄養素と、それを含む食べ物をご紹介します。
1)ビタミンD(免疫調整・炎症抑制)
ビタミンDは、免疫の過剰反応を抑える働きがあり、花粉症の症状を軽減する可能性があるといわれています。さらに、粘膜の健康維持にも関与しているため、鼻やのどの粘膜を強くし、アレルゲンの侵入を防ぐサポートをしてくれます。
| ビタミンDを多く含む食べ物 |
|
💡ポイント:ビタミンDは「油と一緒」に摂ると吸収率アップ!
例えば、鮭のホイル焼きをオリーブオイルで仕上げたり、きのこを炒めたりすると、効率よく摂取できます。
2)オメガ3脂肪酸(抗炎症作用)
オメガ3脂肪酸には、体内の炎症を抑える働きがあり、花粉症による鼻水やくしゃみ、目のかゆみを軽減する効果が期待できます。特に、アレルギー反応を和らげる「EPA」や「DHA」が豊富な食材を意識的に摂るのがおすすめです。
| オメガ3脂肪酸を多く含む食べ物 |
|
💡ポイント:オメガ3は「熱に弱い」ので、生で摂るのがベスト!
例えば、サバ缶をそのままサラダにのせたり、えごま油をスープやヨーグルトにかけたりすると、効果的に摂取できます。
3)ポリフェノール(抗酸化&抗アレルギー作用)
ポリフェノールは、抗酸化作用が高く、アレルギー症状の緩和に役立つ成分です。特に、「カテキン(緑茶)」「フラボノイド(カカオ・ベリー類)」「ケルセチン(玉ねぎ)」などは、ヒスタミンの放出を抑えることで、花粉症によるくしゃみや鼻水を軽減する可能性があります。
| ポリフェノールを多く含む食べ物 |
|
💡ポイント:ポリフェノールは「継続して摂取」することが大事!
毎朝、緑茶を飲む習慣をつけたり、食後のデザートにカカオチョコを取り入れたりすると◎。
4)亜鉛(粘膜の健康維持)
亜鉛は、鼻や喉の粘膜を健康に保ち、花粉が体内に侵入するのを防ぐ重要なミネラルです。また、免疫機能を正常に保つ働きもあり、アレルギー症状の軽減にも役立ちます。
| 亜鉛を多く含む食べ物 |
|
💡ポイント:ビタミンCと一緒に摂ると吸収率アップ!
例えば、牡蠣にレモンをかけたり、ナッツとフルーツを組み合わせたスムージーを作るのがおすすめです。
2.花粉症の方におすすめの食べ物7選
.jpg)
花粉症の症状を軽減するためには、免疫バランスを整え、炎症を抑える栄養素を含む食べ物を積極的に摂ることが大切で、特に、ビタミンD・オメガ3脂肪酸・ポリフェノール・亜鉛 などの栄養素が豊富な食材がよいことがわかったところ、続いて、これらの栄養素が含まれている食品7つを、おすすめな順にご紹介します。
1:鮭(ビタミンD・オメガ3脂肪酸)
鮭は、ビタミンDとオメガ3脂肪酸を同時に摂取できる優秀な食材 です。ビタミンDは免疫の過剰反応を抑え、オメガ3脂肪酸には抗炎症作用があり、花粉症の症状を和らげる効果が期待できます。
オリーブオイルで焼いたり、蒸してレモンをかけると、栄養の吸収率がアップします。
2:納豆(亜鉛・乳酸菌)
納豆は、腸内環境を整える乳酸菌 を含み、さらに粘膜の健康を維持する亜鉛 も豊富に含まれています。腸内環境が整うことで、免疫の過剰反応を抑え、花粉症の症状を軽減する助けになります。
キムチやオクラと組み合わせると、腸活効果がさらにアップします。
3:緑茶(ポリフェノール・カテキン)
緑茶に含まれるカテキンには強力な抗酸化作用があり、アレルギー症状を抑える効果 が期待できます。さらに、殺菌作用もあるため、のどの不快感や炎症の予防にも役立ちます。
一日に数回飲むことで、ポリフェノールをこまめに補給できます。
4:牡蠣(亜鉛)
牡蠣は、亜鉛を豊富に含む食品の代表格 です。亜鉛は鼻や喉の粘膜を健康に保ち、アレルゲンの侵入を防ぐのに役立ちます。
レモンをかけると、ビタミンCの働きで亜鉛の吸収率がアップします。
5:ブルーベリー(ポリフェノール・アントシアニン)
ブルーベリーには、ポリフェノールの一種であるアントシアニンが豊富に含まれており、アレルギー症状を和らげる効果 が期待できます。また、目のかゆみ対策にもおすすめです。
ヨーグルトに混ぜて食べると、乳酸菌とポリフェノールを同時に摂取できます。
6:えごま油(オメガ3脂肪酸)
えごま油には、炎症を抑えるオメガ3脂肪酸が豊富 に含まれており、花粉症による鼻水やくしゃみ、目のかゆみを軽減する効果が期待できます。
熱に弱いため、サラダやスムージーにかけて摂取するのがおすすめです。
7:玉ねぎ(ポリフェノール・ケルセチン)
玉ねぎには、ポリフェノールの一種であるケルセチンが含まれており、ヒスタミンの放出を抑える働き があります。そのため、くしゃみや鼻水などのアレルギー症状を軽減するのに役立ちます。
スライスしてサラダに加えると、ケルセチンを効果的に摂取できます。
3.花粉症シーズンにおすすめの食べ方&簡単レシピ

花粉症対策には、栄養素を「どう摂るか」も重要です。単体で摂るよりも、組み合わせや調理法を工夫することで吸収率が高まります。
具体的なポイントは次の通りです。
- ビタミンDは油と一緒に摂る:脂溶性なので、オリーブオイルなどと調理すると吸収率が上がります。
- オメガ3脂肪酸は加熱を控える:熱に弱いため、スムージーやドレッシングで摂るのがおすすめです。
- ポリフェノールは毎日こまめに摂取:緑茶やベリー類を習慣的に取り入れると効果的です。
- 亜鉛はビタミンCとセットで摂る:牡蠣にレモンをかけたり、大豆と野菜を組み合わせたりすると効率よく摂取できます。
このポイントを踏まえて、簡単なレシピをご紹介します!
抗アレルギースムージー(朝食・おやつにぴったり)
| 🥄材料(1人分) |
| バナナ1本(エネルギー補給) ブルーベリー50g(ポリフェノール) 豆乳200ml(大豆イソフラボン&亜鉛) えごま油小さじ1(オメガ3脂肪酸) はちみつ小さじ1(抗菌作用) |
🥄作り方
- バナナをミキサーに入れやすい大きさにカットする
- 全ての材料をミキサーに入れて攪拌する
- お好みでレモン汁を少し加えると、ビタミンCも摂取できておすすめです。
ポリフェノール&オメガ3脂肪酸がたっぷりのスムージーで、花粉症シーズンの免疫バランスを整えましょう!
免疫力アップ!鮭ときのこのホイル焼き(夕食におすすめ)
| 🥄材料(2人分) |
| 鮭2切れ(ビタミンD) しめじ・えのき100g(ビタミンD&食物繊維) 玉ねぎ1/2個(ケルセチン) オリーブオイル大さじ1(吸収率アップ) レモン1/2個(ビタミンC) 塩・こしょう適量 |
🥄作り方
- アルミホイルに鮭、きのこ、スライスした玉ねぎをのせる。
- オリーブオイルをかけ、塩こしょうで味付けする。
- ホイルを閉じて、オーブンまたはフライパンで蒸し焼きにする(180℃で15分)。
- 仕上げにレモンを絞って完成!
鮭のビタミンD&玉ねぎのポリフェノールを一緒に摂れる、免疫バランスを整える一品です。
粉症対策の腸活みそスープ(腸内環境を整えて免疫力アップ)
| 🥄材料(2人分) |
| だし汁400ml 味噌大さじ2(発酵食品) 納豆1パック(乳酸菌&亜鉛) わかめ10g(ミネラル豊富) 豆腐1/2丁(大豆イソフラボン) ネギ適量(抗菌作用) |
🥄作り方
- だし汁を温め、味噌を溶き入れる。
- わかめ・豆腐を味噌汁に加える。
- 包丁で細かく刻んだ納豆とネギを加えて、軽く温めたら完成!
納豆を入れることで、腸内環境を整え、免疫の過剰反応を抑える効果が期待できます。
4.花粉症対策は腸内環境を整えるとさらに効果的

花粉症対策と聞くと、マスクや食事改善を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は「腸内環境を整えること」も大切なポイントです。
なぜなら、免疫の約70%は腸に集中しているから。
腸内環境が乱れると免疫バランスが崩れ、アレルギー反応が過剰になりやすくなるのです。
ここでは、腸と花粉症の関係、そして腸内環境を整える食事のポイントを解説します。
1)腸内環境と花粉症の深い関係
腸は「第2の脳」とも呼ばれ、健康を左右する重要な器官です。特に、腸内には100兆個以上の腸内細菌(腸内フローラ)が存在し、免疫機能を調整する役割を担っています。
しかし、腸内環境が乱れると悪玉菌が増え、免疫システムが過剰に反応しやすくなります。その結果、花粉に対して過剰なアレルギー反応が起こり、症状が悪化してしまうのです。
つまり、腸内環境を整えれば免疫の暴走を防ぎ、花粉症の症状を軽減する可能性があるというわけです。
2)腸内環境を整える食事のポイント
花粉症対策には、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことがカギになります。そのために、次のような食品を意識して摂ることがおすすめです。
①発酵食品で善玉菌を増やす
発酵食品には乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が含まれており、腸内環境を整える働きがあります。
<おすすめの発酵食品>
- ヨーグルト(乳酸菌・ビフィズス菌)
- 納豆(ナットウキナーゼ&乳酸菌)
- 味噌・ぬか漬け・キムチ(植物性乳酸菌)
💡ポイント:毎日少しずつ継続して摂ることが大切!
②食物繊維で腸内フローラを育てる
善玉菌を増やすためには、エサとなる「食物繊維」も一緒に摂ることが重要です。
<おすすめの食物繊維が豊富な食品>
- 野菜(ごぼう、キャベツ、にんじん)
- きのこ類(しいたけ、しめじ)
- 海藻(わかめ、ひじき)
💡ポイント:「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」をバランスよく摂るのが理想!
③酪酸菌を摂取して腸のバリア機能を強化
最近注目されているのが「酪酸菌」という腸にとって重要な善玉菌。腸内のバリア機能を強化し、アレルギー症状を抑える働きが期待されています。
<酪酸菌を含む食品>
- ぬか漬け
- 発酵バター
- 大麦(もち麦)
💡ポイント:日本の伝統食品「ぬか漬け」には、乳酸菌と酪酸菌が両方含まれているので◎!
5.花粉症&腸活におすすめのサプリ「BIOPORT」

腸内環境を整えることが花粉症対策に役立つと分かっても、「毎日発酵食品や食物繊維をしっかり摂るのは難しい…」という方も多いのではないでしょうか?
そんなときにおすすめなのが、腸内環境を整える乳酸菌&酪酸菌を効率よく摂取できるサプリメントです。特に、「BIOPORT(ビオポート)」は、日本人に合った腸活サプリとして注目されています。
1) 花粉症対策には乳酸菌と酪酸菌
BIOPORTにはいくつかの種類の腸活サプリがありますが、花粉症対策として、腸内環境を整え、免疫バランスをサポートするのにおすすめなのは、乳酸菌と酪酸菌です。
①LIG高濃度乳酸菌(乳酸菌が花粉症の免疫バランスを調整)
「LIG高濃度乳酸菌」は、花粉症に関する臨床試験において、10~12週間の継続摂取後に症状の改善が確認された注目の乳酸菌です。(加熱処理された菌)
免疫バランスを整える働きがあり、鼻水やくしゃみ、目のかゆみといった花粉症の不快な症状を軽減することが期待されています。
<LIG高濃度乳酸菌の特徴>
- 免疫グロブリン(IgE)の過剰な働きを抑え、免疫のバランスをサポート
- 継続的に摂取することで、花粉症の症状を和らげる可能性がある
②CB酪酸菌(腸のバリア機能を強化し、アレルギーを抑制)
「CB酪酸菌」は、腸内の悪玉菌の増殖を抑え、腸内環境を整える働きがあります。
また、アトピー性皮膚炎のマウス試験では、抗アレルギー作用が確認されており、花粉症の症状緩和にも役立つ可能性が期待されています。
<CB酪酸菌の特徴>
- 大腸菌やウェルシュ菌、黄色ブドウ球菌などの悪玉菌を抑制
- 腸の粘膜を健やかに保ち、免疫機能をサポート
- 腸内のビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整える
2)「BIOPORT」はこんな方におすすめ!
腸活サプリ「BIOPORT」は、次のような方にとくにおすすめです。
✔花粉症の症状を少しでも和らげたい
✔ヨーグルトや発酵食品を毎日摂るのが難しい
✔便秘や腸の不調を改善しながら花粉症対策をしたい
✔腸内環境を整えて、免疫バランスを正常に保ちたい
BIOPORTの高品質で日本人に合った乳酸菌&酪酸菌を摂ることで、腸から免疫を整えることが期待できます。そのため、花粉症だけでなく、お肌の調子が気になる方や腸活を始めたい方にもおすすめです。
【今だけ!】お得なキャンペーン実施中!
ただいま、エイジングケア化粧品ナールスで、腸活サプリBIOPORTの「LIG高濃度乳酸菌」と「CB酪酸菌」のセットが25%オフで買えるキャンペーンを実施中。
通常12,960円のところ→25%オフの9,720円(税込)に!
今年は花粉が非常に多いので、いつもの花粉対策に加えて、腸活サプリを取り入れてみませんか?
ぜひお得なこの機会に試してみてください。
※便秘にお悩みの方向けのセットもご用意しています
6.花粉症対策の食事&栄養に関するよくある質問(FAQ)
Q1.花粉症に効く食べ物を食べたらすぐに効果が出ますか?
花粉症対策の食べ物は、即効性はなく、継続的に摂取することで体質改善につながると考えられています。特にビタミンDやオメガ3脂肪酸は、免疫のバランスを整える働きがあるため、毎日意識的に摂取することが大切です。
Q2.花粉症を悪化させる食べ物はありますか?
糖質や加工食品、アルコール、乳製品の摂りすぎは、腸内環境を乱し、炎症を引き起こす可能性があります。特に高糖質な食事(白米・パン・お菓子など)は、腸のバリア機能を低下させるため、花粉症シーズンは控えめにするのがおすすめです。
Q3.いつから花粉症対策の食事を始めればいいですか?
理想は、花粉が飛ぶ2~3ヶ月前からの対策ですが、花粉シーズン中でも遅すぎることはありません!「今からでも間に合う花粉症対策」として、腸活+栄養バランスを整える食事を取り入れるのがおすすめです。
Q4.食事だけで花粉症は改善できますか?
食事は大切な要素の一つですが、完璧に症状を抑えるわけではありません。外的対策(マスク・花粉ガードスプレー)や、腸内環境を整える腸活を組み合わせることで、より効果的な花粉症対策ができます。
Q5.サプリと食事、どちらを優先すべきですか?
基本はバランスの取れた食事ですが、腸活や免疫バランスをサポートするサプリをプラスすることで、より効率的に花粉症対策ができます。特に、BIOPORTのLIG高濃度乳酸菌&CB酪酸菌は、腸内環境を整えて免疫バランスをサポートするため、花粉シーズンの強い味方になります。
7.まとめ:食事+腸活で花粉症対策を!

花粉症のつらい症状を軽減するには、マスクや薬だけに頼るのではなく、内側からのケアも大切です。特に、食事と腸内環境の改善は、免疫バランスを整え、花粉に過剰反応しにくい体をつくるサポートになります。
花粉症対策として、まずはビタミンD、オメガ3脂肪酸、ポリフェノール、亜鉛などの栄養素を積極的に摂ることをおすすめします。また、ビタミンDは油と一緒に摂る、オメガ3脂肪酸は加熱を避ける、ポリフェノールは継続して摂取するなど、吸収率を高める食べ方を意識することで、より効果的に栄養を取り入れることができます。
さらに、腸内環境を整えることも花粉症対策には欠かせません。発酵食品や食物繊維を積極的に摂ることで善玉菌を増やし、腸のバリア機能を強化することが大切です。しかし、毎日の食事だけで腸内環境を整えるのが難しい場合は、乳酸菌や酪酸菌を含むサプリメントを活用すると、効率よく腸活を続けることができます。
毎日の食生活を少し意識するだけで、花粉症の症状を軽減できる可能性があります。
今年の春は、食事と腸活を取り入れて、内側からの花粉症対策を始めてみませんか?
腸活を手軽に続けるためには、BIOPORTのようなサプリメントを活用するのもおすすめです。お得なキャンペーンも実施中なので、ぜひチェックしてみてください。
花粉に負けない体づくりをして、今年の春を快適に過ごしましょう。
花粉による肌荒れ「花粉症皮膚炎」は治療とスキンケアで保湿
腸内時計に合わせた発酵食品の食べ方で美肌も免疫力UPも!
腸活は効果なし?便秘が改善できる自分に合うやり方とおすすめサプリ
【2024年版】乳酸菌サプリのおすすめと選び方|腸活で便秘改善&免疫力アップを目指そう
ありがとうございます。
ナールスゲン配合化粧品の通販サイト「ナールスコム」をよろしくお願い申し上げます。
SNS Share
\ この記事をシェアする /

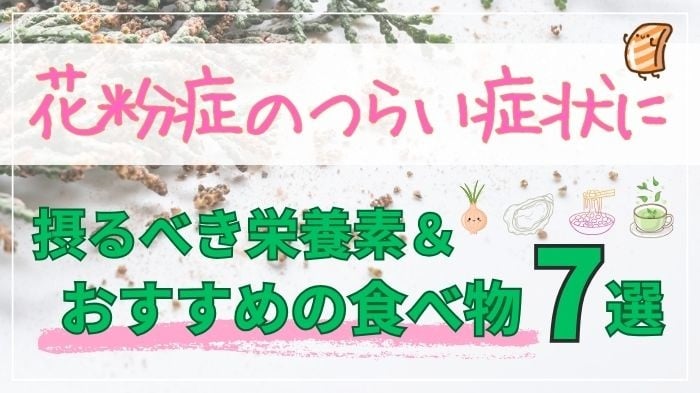
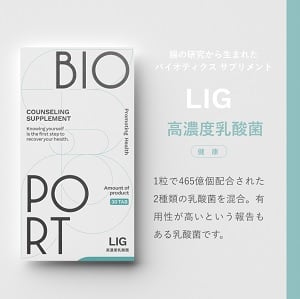
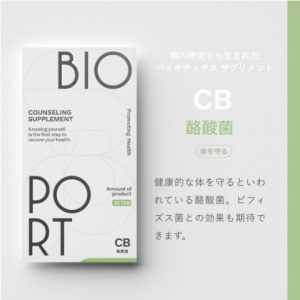

.jpg)
